2020年に新型コロナウイルスのパンデミックが起こり、「人生なにが起こるか分からない」と感じた人も多いと思います。
そんな不安感から株式市場や債券市場といったあらゆる市場が暴落し、ワクチンが開発されるまで不安定な相場が続きました。
Twitter上でもロスカット(強制決済)や投資の世界から退場するというツイートが溢れていました。
投資はリスクのあるお金の増やし方なので、リスク管理がとても大切です。
リスク管理にはたくさんの方法がありますが、わたしは損失許容額内で運用して、暴落や下落相場を乗り越え、退場しないようにすることが1番大切だと思っています。
今回は損失許容額についてお伝えします。
- 損失許容額の考え方や決め方について知りたい
- ポートフォリオを考えたor見直したいと思っている
このように思っている人は、ぜひ読んでみてください。
Contents
損失許容額の考え方「暴落には必ず直面する」
「暴落が起こる前に売却する」。これができれば暴落に備える必要はありません。
ポートフォリオの見直しもアセットアロケーション(資産配分の割合)について深く考える必要もありません。
でも、暴落が起こるタイミングなど投資の専門家でも分からないもの。素人が正確に予測することは不可能です。
暴落を避けることはできない。暴落はいつか必ず起こり、直面するモノだと考えてください。
わたしは投資を辞めるつもりはありませんし、これからも運用し続けるつもりです。いつか必ず暴落にあうと覚悟しています。
大切なことは、日ごろから暴落を前提とした資金管理をすることです。
世界経済は、リーマンショックやイギリスのEU離脱、チャイナショックなど様々な危機に直面してきましたが、結果的に回復しています。
長期的に見ると、緩やかに上昇し続けているのです。
いつまでも下がり続ける相場はありません。いつかは必ず下げ止まり、上昇し始めます。
問題は下落がいつまで続くか分からないということ。
暴落・下落相場をやり過ごすためには、普段から暴落に備えて対策をする必要があります。
暴落に備えるとは、暴落に直面して一時的に損失を出すことになっても、損失額を自分が耐えられる額=損失許容額にして、暴落をやり過ごして退場しないようにすることだと考えています。
【損失許容額はいくら?】損失許容額は自分で決めるしかない
損失許容額については、いろいろな考え方があります。
「自分の収入の1年分を確保してあとは投資に回す」、「資産の50%を積極的な投資に回す」など様々な意見や考え方、データ、理論、仮説が存在していますが、あくまでも参考にしかなりません。
自分が耐えられる額は、自分の価値観や環境、お金との向き合い方で変わるからです。
20代の人と60代の人では現金比率は違うでしょうし、投資で資産1億円突破したいという人と3000万円突破を目指している人の運用額は違います。
自分がどんな運用をしたいかをしっかり考えて、損失許容額を決めてみてください。
さて、自分の損失許容額を決める上で、参考になる4つの考え方をご紹介します。
- 自分の総資産から損失許容割合を考える
- 自分の損失許容額を自分の年間貯金額から考える
- 生活防衛資金以外を損失許容額として考える
- 自分の気持ちから考える
総資産から損失許容割合を考える
1つ目は、自分の総資産の〇〇%を積極的な投資に回すという考え方です。
自分の許容額というより、自分が耐えられる割合(損失許容割合)を考える方法になります。
例えば資産が1000万円あった場合、約3割は「いつでも使えるお金」として銀行に預けておく、残り7割を積極的に運用していくという風に考えます。
投資で資産が増えれば、割合が変わらないようにリバランスをしていきます。
わたしは資金を3つにわけて考えています。
- 流動性資金(生活防衛資金):生活資金など毎日必要なお金や急な出費の際にいつでも引き出せるお金
- 安全性資金:住宅購入や自家用車の購入、教育資金など今すぐではないが貯めていきたいお金
- 収益性資金:積極的に運用するお金
流動性資金は生活費の1年分程度を普通預金に、夫婦共同の資金は安全性資金として定期預金で預けています。
ポイ活や副業で得た資金は収益性資金として積極的に運用しています。
自分の損失許容額を自分の年間貯金額から考える
もう1つは、自分の年間貯金額から考える方法です。自分の耐えられる最大損失額を自分の年間貯金額×何年で考えるということです。
例えば、1年で100万円貯めることができて、最大損失額を1年間の貯金額で抑えたいとします。
まずは運用している投資の期待リターンとリスクを計算します。
下の表は、日本の年金を運用している年金積立管理独立行政法人(GPIF)が2020年の「基本ポートフォリオの変更について」において、資産クラスの期待されるリターンとリスクを推計したものです。
| 期待リターン | リスク | |
| 国内株式 | 約5.6% | 23.14% |
| 外国株式 | 約7.2% | 24.85% |
| 国内債券 | 約0.7% | 2.56% |
| 外国債券 | 約2.6% | 11.87% |
期待リターンとリスクは、投資している金融商品と投資額が分かれば、無料ツールを使って計算することもできます。
わたしは「投資信託のガイド/ファンドの森」のアセットアロケーション分析を使いました。
計算した結果リスク20%だったとします。
10年に1回起こると言われる暴落では想定されるリスクの2倍の下落が起きると言われていて、100年に1度と言われたリーマンショックのときは、想定リスク×3倍の損失が起きました。
このことから、リーマンショック級の暴落が起きた場合、最大損失は60%になると考えられます。
100万円で運用していたとしたら、評価額が40万円になるということです。
最大損失額を100万円以内にしたい場合、165万円が運用できる最大額となります。
生活防衛資金以外は積極的に運用する
生活防衛資金とは、何かあったときにすぐに使えるお金のことです。
収入×3か月~1年分程度はあった方がいいと言われています。
新型コロナウイルスが流行して痛感していますが、異常事態は数か月どころか数年以上続くこともあるのです。
1年分、大体200~300万円は生活防衛資金として用意しておいた方がいいと思います。
暴落や下落相場は長い場合は1~2年続くと言われ、回復には5年程度必要だと言われています。
しばらくまとまったお金を使う予定がない人は、生活防衛資金以外は運用するという考え方もあります。
自分の損失許容額の考え方「自分自身の気持ち」
リスクと期待リターンから損失許容額を考えることもできますし、資産割合から損失許容額を考えることもできます。
でも、わたしは1番大切なのは自分の気持ちだと思っています。
損失許容額を考えても、夜ゆっくり眠れないようなら損失許容額を超えているということです。
理屈ではない自分の気持ちが最終的には1番大事かなと思います。
【注意】損失許容額や最大損失額を把握していないと、暴落で投げ売りしやすい
この額までなら一時的に損失を出しても問題ないという損失許容額を曖昧にしか決めていなかったり、資産運用をしている時に起こる最大損失額を把握していないと、暴落が起きた時に焦って投げ売りしやすくなります。
新型コロナウイルスにように、予期せぬ事態が起きるときもあります。
投資を始める前にお金との向き合い方や投資運用のスタイル、最大損失額を把握して損失許容額をしっかり決めておくことが投資の大前提です。
暴落を乗り越えれるように、損失許容額はしっかり決めてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
にほんブログ村のランキング参加中。記事が参考になったら、ぜひ応援クリックお願いします!
にほんブログ村
投資への考え方に関する記事一覧
- 【実践した感想付き】コア・サテライト戦略と分散投資の違いは?
- 生活防衛資金はいくら必要?最低でも生活費の1年分貯めた方がいいと思う理由
- 生活防衛資金が貯まっていなくても投資を始めた方がいいと思う2つの理由
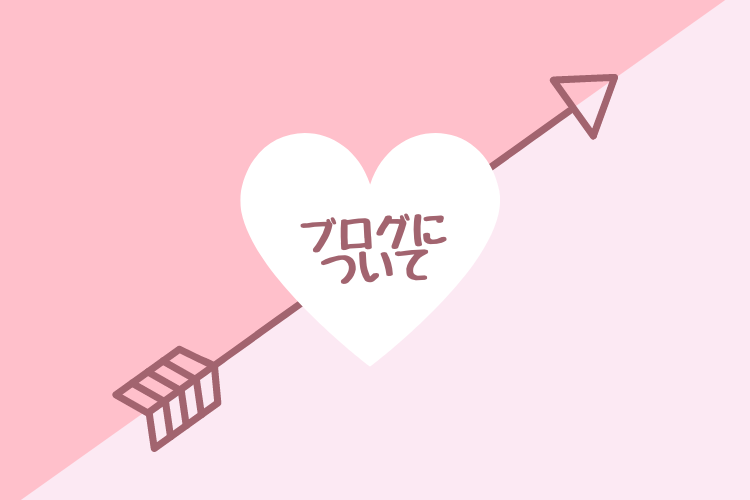
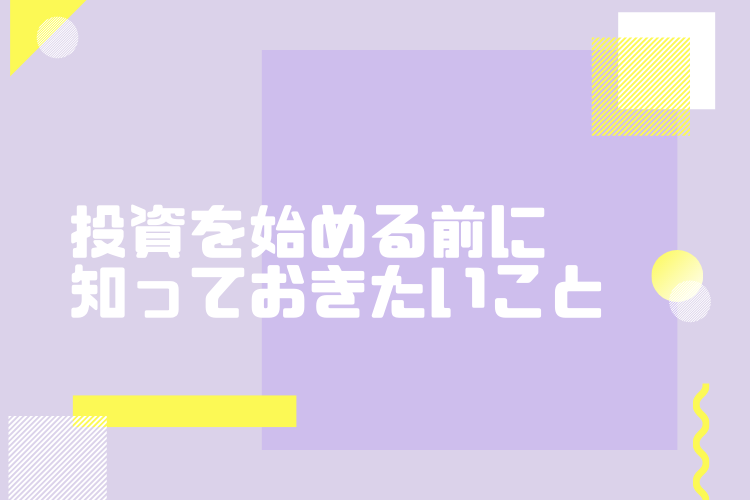
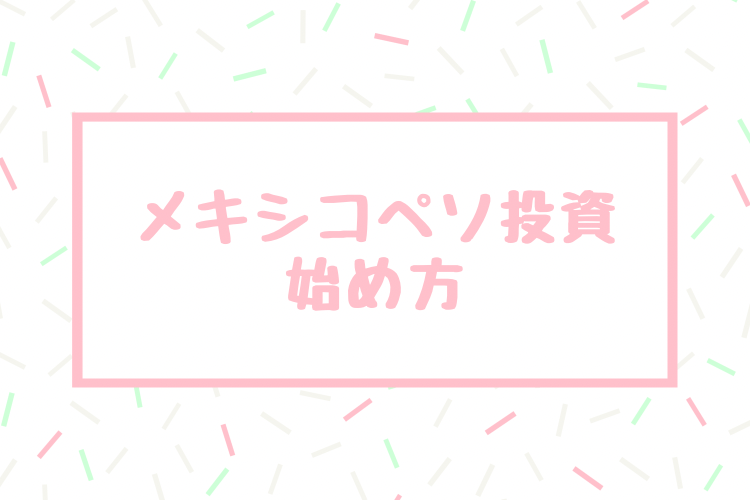
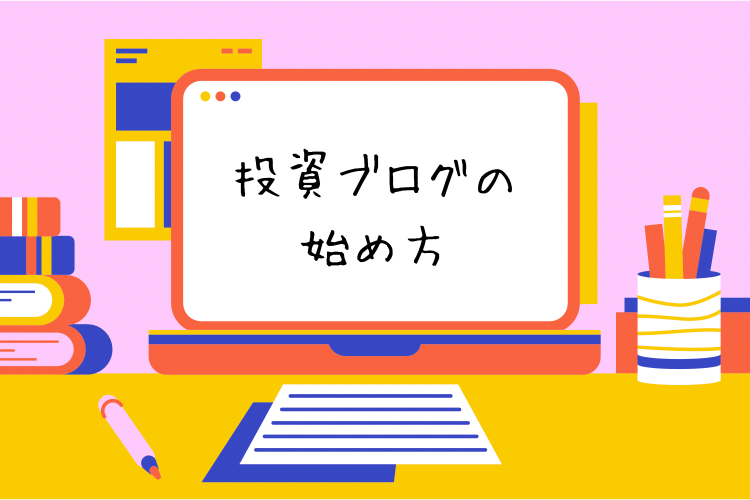
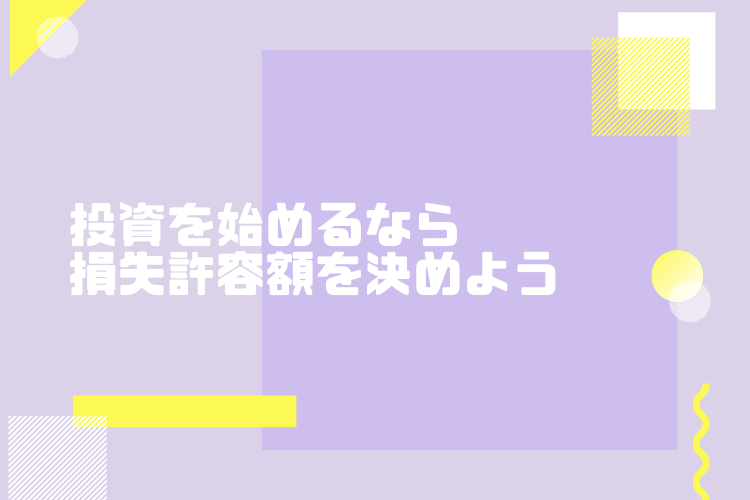
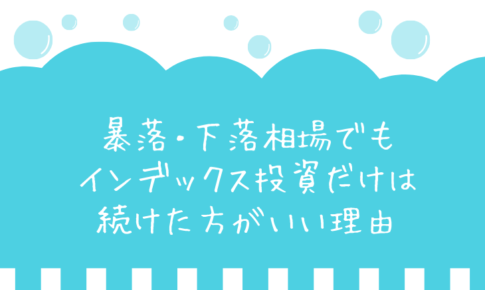
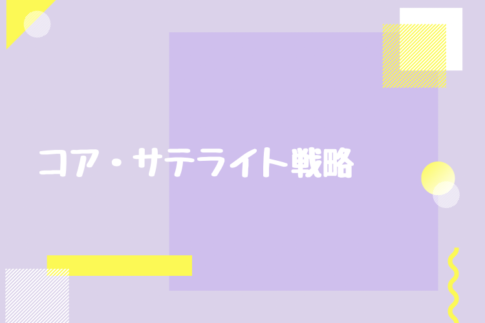
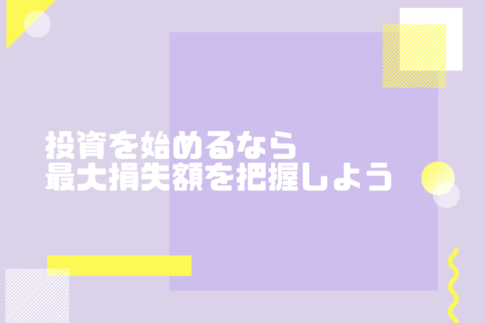
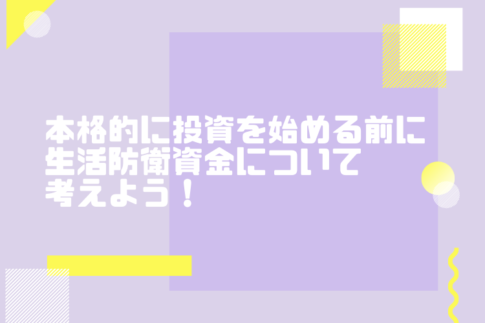
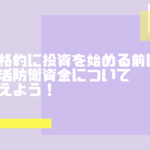
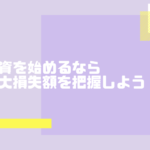
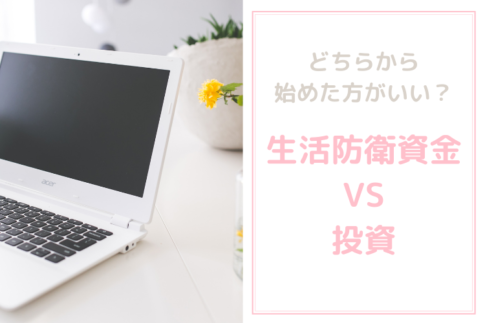
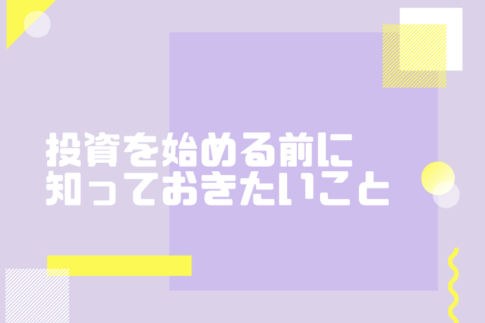

こんにちは、投資ブロガーとうなです